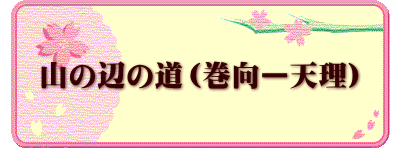8.長岳寺
トレイルセンターで弁当を食べてから、コース外になるが長岳寺に寄る。ちょうど紅葉がきれいで訪問者が多い。ただ、写真を撮るだけだったのでお参りはしたが15分程度で出てしまった。
長岳寺(ちょうがくじ)は高野山真言宗の寺院。山号は釜の口山(かまのくちさん)、本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は空海(弘法大師)とされる。天長元年(824)に淳和天皇の勅願により空海が大和神社の神宮寺として創建した。盛時には48もの塔頭が建ち並んでいた。という。
7.天理市トレイルセンター
崇神天皇陵を通過して集落の道を降りると休憩所がある。愛称は青垣トレイルセンターだが、天理市トレイルセンターが正式名称になっているようだ。
東海自然歩道上に建つ、休憩と観光情報提供を兼ねた施設。館内には東海自然歩道や山の辺の道散策案内、卑弥呼の鏡で知られる三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)が33面も出土した黒塚古墳の石室模型(約1/4に縮小)を、展示。
湯茶の設備や各種案内パンフレットがおいてあり、テーブル椅子もあり食事もできる場所だ。常駐の係の人もいるので周辺のことなど聞くこともできる便利な場所だ。また、近くには食堂も数軒あり、昼食場所に事欠かないようだ。天理や桜井からくるとちょうど食事時になる場所でもあるようだ。
外廻りにも座れる場所や休憩に適した庭が配置されていて、憩いの場所にもなる。駐車場もあるので車で訪れる人も多いようだ。この横には長岳寺があり、ここの紅葉鑑賞に観光バスも数台きていた。
(中)
崇神天皇陵の反対側にも櫛山古墳があり、その池が少し紅葉に染まっていたので記録した。
6.崇神天皇陵
ここから少し歩くと、崇神天皇陵になる。行燈山古墳(あんどんやまこふん)は、古墳時代前期の前方後円墳(帆立貝形古墳にも分類される)。宮内庁により「山邊道勾岡上陵(やまのべのみちのまがりのおかのえのみささぎ)」として第10代崇神天皇の陵に治定。
墳丘は全長が242メートル、正円形で3段築成の後円部は直径158メートル、高さ23メートル。後円部頂上は平坦で円形。前方部正面は、わずかであるが弧状。その頂上は、くびれ部に向かって少しずつ低く坂のように整形されている。渡り土堤が後円部南側と前方部にあり、築造当初から設けられていたと推定。周濠の形状は左右対称の盾形。とある。
崇神天皇(すじんてんのう)は、『古事記』『日本書紀』に記される第10代天皇。現代日本の学術上、実在可能性が見込める初めての天皇であると言われる。日本史研究の立場からは崇神天皇を初代天皇、あるいは神武天皇と同一人物であるとする説がある。崇神天皇を大和朝廷の礎を築いた存在とした場合、邪馬台国と崇神天皇のかかわりが問題になり、学者により各説あり邪馬台国の存在場所によって異なるのだ。古代史の謎だ。
天皇陵は実際は何もないので通過するだけである。
山の辺の道は古墳が多い。すべて見ていたら時間もかかる。代表的となると天皇陵になるが、これも宮内庁管轄というだけで実際のところは考古学者は判らないという。内部を完全に検証できていないからだ。
5.景行天皇陵
渋谷向山古墳(しぶたにむこうやまこふん)(景行天皇陵)は、全長310メートル、前方部幅170メートル高さ23メートル、後円部径168メートル高さ23メートル。墳丘は東西方向に主軸をおき、後円部は正円形で3段築成、前方部も3段で築かれている。後円部頂上は平坦で円形。前方部の頂上も平坦であり、長い台形。
宮内庁により「山邊道上陵(やまのべのみちのえのみささぎ)」として第12代景行天皇の陵に治定。現在は景行天皇陵に治定されているが、江戸時代には崇神天皇陵と思われていた。築造年代は現在の崇神天皇陵である行燈山古墳より少し遅れた4世紀後半と推定される。という。
景行天皇は、垂仁天皇の第三皇子、母は日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)で、皇后播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ) 若建吉備津日子女との間に小碓尊(おうすのみこと、日本武尊)が繋がる。『古事記』『日本書紀』に記されているが実在したかは判らない時代だ。垂仁天皇の親が崇神天皇になる。