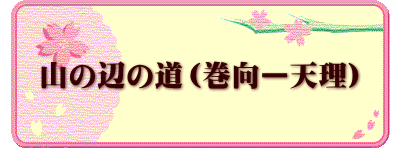石上神宮をでて天理市街になり、天理教関係の建物ばかりが目立つ、一帯は天理教の都のようなものだ。宗教には触れたくないのでここは割愛し、天理本通り商店街を歩き天理駅にくる。JRと近鉄の駅が隣接していて、駅前広場は整備されて広くなっている。
今回の山の辺の道歩きはここで終わりだ。説明が飛び飛びになってしまったが、資料を調べれば調べるほどにどこまで載せるかの迷いがあり、省略することが多くなってしまった。
また、機会があれば歩いてみたいコースである。
写真 1段左:天理商店街 1段右:天理のゆるきゃら人形
2段左:天理駅 2段右:駅前ビル改装中?
13.石上神宮
池のほとりを過ぎていよいよ石上神宮の敷地に入る。 ここは団体ツアーが観光バスでくるようで、バスガイドさん数名が6台の人もどういう順で案内するか話している声尾が聞こえた。やや年配のグループのようだ。老人会か町内会か。
古代の山辺郡石上郷に属する布留山の西北麓になる。古い歴史があり『古事記』・『日本書紀』に既に、石上神宮・石上振神宮との記述があり、古代軍事氏族の物部氏が祭祀し、ヤマト政権の武器庫としての役割も果たしてきたと考えられる。
時代ごとの権力者の庇護の下に拡大しているが、中世以降は興福寺と度々抗争を繰り返し布留郷一揆が頻発、戦国時代に入ってからは織田信長の勢力に負け、神領も没収。しかし、明治になって政府の計らいで復活した。先の永久寺とは逆になるのだ。
12.内山永久寺跡
一休みした後は、石上神宮に向かう。やや急坂がありゆっくりと歩くが神社やお寺の急坂を思えば緩やかなものだ。ただ、1ケ所だけは急な石の坂があるので、ここは避けて少し遠回りした。石の坂はもし転ぶと下まで転げていきそうなくらいの急なところだった。
柿の農園は道の横に続き、もう刈った後だが手が届きそうなくらいに低くしている。収穫目的の柿栽培をしているのだ。また、蜜柑類も山の辺の道によく植えてあって、成っている実を摘みたい衝動に駆られる。実際に被害があると思うが、農家はあまり気にしていないのだろうか。
ゆるやかな山道になって、内山永久寺跡の看板がある。内山永久寺(うちやまえいきゅうじ)は天理市杣之内町にかつて存在した寺院。興福寺との関係が深く、多くの伽藍を備え、大和国でも有数の大寺院であったが、廃仏毀釈の被害により明治時代初期に廃寺となった。という。
三方を山に囲まれていることから内山といい、院号を金剛乗院といった。本尊は阿弥陀如来。永久年間(1113年-1118年)に鳥羽天皇の勅願により興福寺大乗院第2世院主の頼実が創建し、第3世尋範に引き継がれて堂宇の整備が進められた。
天正13年(1585)の時点で、56の坊・院が存在。近世の『大和名所図会』所収の境内図によれば、池を中心とした浄土式回遊庭園の周囲に、本堂、観音堂、八角多宝塔、大日堂、方丈、鎮守社などのほか、多くの院家、子院が建ち並んでいた。とある。凄い大きい規模だったことが分かる。明治政府も酷いことをしているのだ。
11.天理観光農園
今回の山の辺の道歩きも終盤に近づいている。天気はいいし足・膝は大丈夫だ。このまま奈良まで歩いてもいけるくらいだ。でも、実際は時間的には無理なことであり天理市街を目指す。
歩いていると天理観光農園の建物が見えてきた。グループや個人が休憩しているので当方も小休止にする。 売店にカフェ、あわ餅つき、バーベキュー、部屋の貸し出しもしている。
またこのシーズンはみかん狩りもできるようだ。約1ヘクタールの園内に早生温州みかん約800本。春はきんかん狩りもあり、ハーブ園をはじめ農園内は、シーズンオフでも自由に散策することができる。という。
抹茶ソフトが一休みにはおいしいものだ。ここで、バーベキューをしたり貸部屋で趣味の会の会合など使い方はいろいろありそうだ。ギャラリーでは、作家やアーティスト、サークルの展示発表会などもできるとある。
写真 下2段はこの後の道筋の風景
(下)
10.夜都伎神社(やとぎじんじゃ)
集落地から1時間ほど歩いて、夜都伎神社で紅葉を見る。夜都伎神社(やとぎじんじゃ)は奈良県天理市にある神社。祭神は、武甕槌命・姫大神・経津主命・天児屋根命。乙木(おとぎ)集落の北端にあり、於都岐(乙木)の誤写とする説もあるらしい。
現在の本殿は明治39(1906)年改築したもので春日造桧皮葺、高欄、浜床、向拝付彩色7色の華麗な同形の四社殿が末社の琴平神社と列んでいる。拝殿は萱葺で珍しい神社建築。鳥居は嘉永元(1848)年奈良の春日若宮から下げられたものといわれる。
山の辺の道を再び辿り、歌碑がところどころあるのだが、今回はパスしてしまった。案内パンフによるとコースには38カ所の歌碑があるそうだ。万葉集からの採用が多いが、古事記や他の少しある。川端康成や棟方志功など有名人の筆によるものがある。
9.環濠集落
ひたすら歩くという感じで念仏寺前を通過し、環濠集落の脇に通じる農道を歩く。付近の古墳の説明看板もあるが、古墳はもう寄らないことになる。
環濠集落は、外敵から身を守るため周りに濠を巡らせた集落のことで、その始まりは室町時代に遡ると言われる。室町時代の戦国期に動乱を受け、自衛の手段として集落の周囲仁濠が設けられた。盆地に所在する集落の多くは、鎌倉・室町時代から続くものが多く、その大半が環濠で囲まれていたと考えられる。
山の辺も道筋では、奈良盆地の東麓、標高約100mの高さに位置し、盆地内では最も高所に造られた環濠集落で、北側に竹之内環濠集落、南側に萱生(かよう)集落が所在する。
写真 1段:念仏寺門前、説教像
2段:大和古墳群案内看板
3段:周辺は農地になっている
4段:左 竹ノ内環濠跡、 右 萱生加豪跡