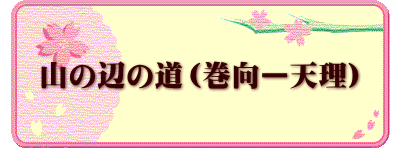大兵主神社で紅葉を楽しんでからは、しばらく元の道を下る。この周辺はミカンやカキの農園があって、ちょうどミカン狩りにきているグループもいる。ミカン狩りをして陽気なおじさん連中が大声で歩いている。すでにいい機嫌になっているようだ。あまり近寄らない方がいい。
道を下って途中から景行天皇陵方面への案内看板が右手にある。入り口は狭い下り坂なのでよく見ていないと見過ごしそうだ。以前に見て知っているので問題はなかった。なお、行き過ぎても巻向集落からも景行天皇方面への道はあるのだ。
山道というか農道の狭い道は山の辺の道という雰囲気で、天気もいいし最高のハイキング日和になった。行き交う人が時々あるが、こんにちはの声も気持がいいものだ。ぜんぜん知らない人でも、こういう場所では素直になるものか。
また、道のところどころで無人販売がある、カキやミカンに野菜などおばちゃんには魅力的な買い物だ。1皿や1袋が100円や200円程度で手頃だ。重くなるのさえガマンすればいい買物になる。そういえばこの線の駅も無人駅が多いが、無人駅で降りる時に横着して料金を払わなくても判らない。日本人の良識に任せているのだ。
説明はないが、山の辺の道らしい風景を撮った
4.大兵主神社
ここから更に、道は上りで大兵主神社に寄る。ここの紅葉が一番きれいだったが、撮った写真ではあまりよくないのが残念だ。名前がいろいろあってどれがいいのか判らないが、資料では穴師坐兵主神社(あなしにますひょうずじんじゃ)とあり、元は穴師坐兵主神社(名神大社)、巻向坐若御魂神社(式内大社)、穴師大兵主神社(式内小社)の3社で、室町時代に合祀された。現鎮座地は穴師大兵主神社のあった場所。とある。
穴師大兵主神社については鎮座年代は不詳で、祭神の「大兵主神」は現在は左社に祀られ、剣を神体とする。大兵主神の正体については、八千戈命(大国主)、素盞嗚命、天鈿女命、天日槍命という説がある。
穴師(アナシ)は地名を指すが、本来のアナシ(穴師・穴磯)とは、穴を掘って鉄鉱石や砂鉄を採取する部族を指す呼称といわれ、そういう穴師部族が附近に居たことから、“穴師”の地名が付いたという。
(上)
3.相撲神社
ここから相撲神社へが冒頭にも述べたが、やや道に迷いながらも坂道を上がってたどり着く。手前には纒向古墳群の看板もあり一帯は古代に古墳が多数存在していたようだ。
相撲神社は、小さなお社がたつだけだが、約2千年前、当麻蹶速と野見宿禰が戦った場所という。『日本書紀』に,当麻村(當麻邑)に當麻蹶速(たいまのけはや)という力自慢がいて,力のある者と試合をしたいと言っていた。そのことを聞いた垂仁天皇は 力持ちとして名を知られていた出雲の国の野見宿禰を呼び寄せ,2人による我が国初の天覧相撲がこの地で催された。
試合の結果は 野見宿禰が蹴速を蹴り技で倒し(腰を踏みくじいて)蹶速は命を失った。天皇は當麻蹶速の土地を野見宿禰に与え,宿禰はこの地にとどまって天皇に仕えたという。古代における武術の争いは 命がけが常識だったのだろうか。日本の国技である相撲のはじまりとされる。という。
2.ホケノ山古墳
箸墓古墳の近くにはホケの山古墳がある。ホケノ山古墳(ほけのやまこふん)は、古墳時代前期初頭の纒向型といわれるホタテ貝型の前方後円墳。2006年に纒向古墳群の一つとして国の史跡に指定された。被葬者は不明で、大神神社は豊鍬入姫命の墓としている。という。
山の辺の道は何回か歩いているが、紅葉の頃も見映えのある景色が楽しめる。山の辺の道は大和の古代道路のひとつ。、奈良盆地の東南にある三輪山のふもとから東北部の春日山のふもとまで、盆地の東縁、春日断層崖下を山々の裾を縫うように南北に通ずる古道。
弥生時代後期には、布留遺跡と纏向遺跡を結ぶ道であったとも推測されている。全長は約35kmであるが、その南部に古道の痕跡や景観が残り、現在、一般的には天理市の石上神宮から桜井市の大神神社付近までの約16kmの行程である。
通常は桜井か三輪から天理になるが、今回は少し短縮して巻向からの出発になった。しかし、実際は三輪から歩いても変わらぬ距離になったと思うのだ。少し予定を変更して最初に箸墓古墳を目指したが、古墳の回りは何もなくて予定の相撲神社に向かうが、道案内の標識があまりなくて戸惑った。地元の人に確認して本来の道に出るまで30分ほどのロスになった。
巻向駅は無人駅でほとんど乗降客はいない。この駅近辺で巻向遺跡が発掘されたという看板が駅前にあった。近くには箸墓古墳がある。
1.箸墓古墳
箸墓古墳(はしはかこふん、箸中山古墳)は、前方後円墳で、宮内庁により「大市墓(おおいちのはか)」として第7代孝霊天皇皇女の倭迹迹日百襲姫命の墓に治定されている。しかし、考古学者の中には卑弥呼の墓と推定している人もいて、時々話題になる場所である。
写真 2段左:駅近辺で発掘された遺跡の建物想定図
2段右:巻向駅 無人駅 素通りできそうな
3段左:箸墓古墳 3段右:纏向遺跡の説明