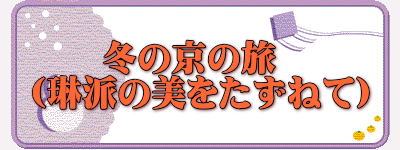食事後の次の目的地は、頂妙寺になる。バスで移動は15分程度か。頂妙寺(ちょうみょうじ)は、日蓮宗の本山(由緒寺院)。山号は聞法山。塔頭が八院(真如院、法輪院、大乗院、善性院、妙雲院、本立院、善立院、真浄院)ある。
下総国出身の僧日祝が、細川勝益から寺地の寄進を受け、文明5年(1473)に頂妙寺を開山した。ここも法難・焼失などで幾多の移転を繰り返している。現在の地には、寛文13年(1673)移転した。しかし、天明8年(1788)の天明の大火により焼失したが。その後再建された。
琳派の絵師・俵屋宗達ゆかりの寺として、冬の旅シリーズでは初めて公開されたという。境内には宗達のものと伝わる墓や、仁王門通の名の由来となった伝運慶作の持国天像と多聞天像を安置した仁王門、本堂などが残る。
下地が乾かないうちに次の色を落とす「たらしこみ」技法で牛の逞しい筋肉を表現した宗達筆「牛図」(重文)ほか、朝鮮の「蓮紙織画」、「三十番神像」、複雑な構造で落し蓋の底に文書を隠した「京都十六本山会合文書箱」などの寺宝が特別展示されている。
「牛図」は、二幅あって、牛が立っているものと、牛が座っているものがある。二幅いっぺんに見られず、この時期は座っている方だが、ボケが多くて牛の輪郭が辛うじて判るくらいか。横に、拡大したレプリカで2軸の絵があるが、立っている牛のほうが牛の顔がまだ見えるかと感じた。通常は京都国立博物館預け。
他の展示品を見て外に出る。運慶伝の仁王門に来るが、仏像は前に網があって中は暗くてあまり見れらない、また仁王門に扁額があるが読めない、豊臣秀吉から布教を許す旨がかかれた手紙を扁額にしたもの。日蓮宗は布教を禁じられた時期があり、布教が許されるようになって、喜びを京都中に知らせるため、その時の許状を扁額にしたものという。
ここは庭園もなくその代わり境内が広いので、バスの駐車もできるのだ。最後に、宗達の墓まで見に行く名前が入っているのを確認しただけ。お墓なのだから特に期待はできないが。