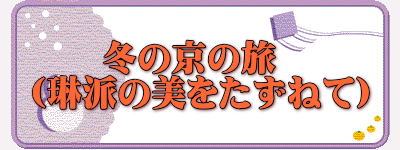頂妙寺からこの日最後の訪問地、建仁寺へ移動する。この付近は八坂神社や円山公園など賑やかな場所で、京都にくるとよく立ち寄る場所であり、建仁寺も何度か来ている。三門は特に目立つ。
今回は、冬の旅の企画に合せて、建仁寺本坊で特別展示を中心に拝観する。俵屋宗達の代表作といわれる風神雷神図(国宝)が入ってすぐにある。金地の二曲一双屏風のそれぞれに風神と雷神を描く。たっぷりと取られた余白が広い空間を暗示し、天空を駆ける両神のダイナミックな動きを感じさせる。とある。
実物は京都国立博物館に寄託している、ここのはニューヨークの展覧会への出展要請を機に、最新デジタル技術とグラフィックデザイナーの色調補正によって、特殊開発された和紙にプリントされたもの。金箔の再現だけは、西陣の伝統工芸師が協力したという。
複製品ということもあってか、撮影は自由にできるので、専門の説明員の説明もそこそこに鑑賞者は撮りまくっている。しかし、前の方にはたくさん人が陣取っていて近寄れず、少し後ろからの撮影となった。ガイドさんが先に行ってしまうので、ゆっくりできないのだ。
建仁寺(けんにんじ)は、臨済宗建仁寺派大本山の寺院。山号は東山(とうざん)。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は源頼家、開山は建仁2年(1202)で栄西(ようさい)により。塔頭寺院は、明治時代の廃仏毀釈により多くが失われ、現在は14院が残る。両足院、常光院、などある。高台寺や法観寺は建仁寺の末寺。
建仁寺は、応仁の乱による焼失のほか、応永4年(1397)、文明13年(1481)などたびたび火災にあい、創建当時の建物は残っていない。受付の方丈(重要文化財)は、室町時代の建物だが、広島の安国寺から慶長4年(1599)に建仁寺に移築したもの。という。
* 写真:2段目 沿革・由緒の石碑 (本坊入り口手前の参道横にあった)
3段目 風神雷神図