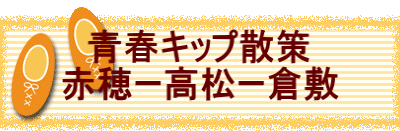2.高松
① 瀬戸大橋
播州赤穂駅から赤穂線で岡山に向い、岡山からマリンライナーで高松に行く。
マリンライナーは、西日本旅客鉄道(JR西日本)と四国旅客鉄道(JR四国)が岡山駅 - 高松駅間を宇野線・本四備讃線・予讃線(瀬戸大橋線)経由で共同運行する快速列車で、昭和63年(1988)瀬戸大橋の完成に伴い、本四備讃線が開通したことにより運転を開始した。
快速「マリンライナー」という愛称はJR西日本による一般公募によって決定された。岡山駅 - 高松駅間71.8kmを52分 - 63分で、基本的に1時間あたり2本運転されている。
瀬戸大橋からの眺めはいいのだが、列車だと橋桁が邪魔になって開けた景色が見られないのが残念だ。上の車道を通行の場合は視界が広くなって景色はもっとよく見えたのだが。
上:瀬戸大橋とマリンライナー 下:高松駅
 ② 玉藻公園・高松城跡
② 玉藻公園・高松城跡
高松駅に着いて予定では高徳線で栗林公園駅の方まで行くことにしていたが、時間的に16時過ぎで高松城跡に入れるので、そちらに行くことにした。
これが良かったかどうか、その後のホテルまで結構歩くことになったのだ。
高松城跡は一度きたことがあるが、随分前のことなので忘れている。実際は40分ほどだが散策した。
高松城は、高松市玉藻町にあった日本の城で、別名・玉藻城(たまもじょう)といわれ国の史跡に指定されている。
別名「玉藻城」は、万葉集で柿本人麻呂が讃岐国の枕詞に「玉藻よし」と詠んだことに因み、高松城周辺の海域が玉藻の浦と呼ばれていたことに由来するとされている。
高松城は、豊臣秀吉の四国制圧の後、天正15年(1587)讃岐1国の領主となった生駒親正によって、「野原」と呼ばれた港町に築かれた。
現在の遺構は、江戸初期に徳川光圀の兄で常陸国から12万石で高松に移封された松平頼重によって改修されたもの。三重櫓や門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存し、城跡は「玉藻公園」として整備されている。
また外堀と内堀には海水が引き込まれており、往時の名残を残している。そのため、堀には牡蠣などの貝が生息し、養殖の鯛も放流されている。
西門から入って天守台跡の展望台に向かうが橋を渡る。本丸と二の丸をつなぐ橋で鞘橋とある。鞘橋の名称は、橋上が露天ではなく屋根と側壁がある廊下橋の構造をしており、それを刀の鞘に見立てたことによるという。
天守台は明治に解体されていたが、修復されて展望台になっているので、そちらの景色をみて城跡内を通り抜けて東門から出た。
和船でお濠の一部を回遊できる体験があったが、時間的には終わっていた。また植木市なども開催しており、市民の憩いの場になっているようだ。
玉藻公園・高松城跡マップ

玉藻公園石碑 入口


天守台説明

上左:鞘橋 周囲のお濠

天守台修理工事説明

上左:天守台跡 上右:天守台跡展望から鞘橋

上左:対岸から鞘橋 上右:天守台跡石垣 下:周囲のお濠
 ③ 高松市商店街
③ 高松市商店街
高松市は、香川県の県庁所在地。旧香川郡・木田郡・綾歌郡からなる。四国の経済の中心地で、国から中核市に指定されている。
平成の大合併などを経て42万人を擁し、さらに高松市を中心とする高松都市圏の人口においては約84万人で、香川県の人口100万人の過半数に達する四国最大の都市圏。
瀬戸内海に面する港町で、かつて国鉄の宇高連絡船が就航していたこともあり、四国の玄関口として四国を統轄する国の出先機関のほとんどや、多くの全国的規模の企業の四国支社や支店、また四国電力やJR四国、四国全域を営業区域とする公共サービス企業の本社などが置かれ、四国の政治経済における中心拠点である。
江戸時代には御連枝の高松松平家(水戸徳川家の分家)が治める高松藩の城下町として盛え、高松城天守がこの街の象徴であったとある。
高松城跡玉藻公園を出て、ガイドブックに載っているコースを歩こうとしたが、方向を間違えてたようで反対方向に行っていた。
途中で地図を見ていたら親切な女性に声をかけられて、方向を教えていただいた。駅の方から行った方がいいと言われていったん、駅前近くに行フェリー乗り場を横にみてベイエリアを行くと北浜アリーがある。
北浜alleyは高松市北浜町にある古い倉庫を活用した複合商業施設。2000年にオープンした高松港ウォーターフロントのトレンドスポット。ギャラリー、ブティック、カフェレストラン、美容院、雑貨店などが入居し、広場ではフリーマーケットやコンサートなどが開催される。
高松港を経由する貨物の一時保管場所として昭和初期に建設され、本四架橋の開通によりその役割を終えた古い倉庫群が「倉庫の現姿を残す」、「商業施設として再生する」、「文化的貢献を果たす」を基本理念として、農業協同組合・JA香川県などにより開発された施設。
しかし、この日は終わりに近づいていたようで、閉まっている店もあり活気はぜんぜんなくて暗かった。
左:フェリー乗り場 右:北浜アリー

前を通過して次に向かうのだった。苦労したが期待外れの感じであった。ここからまた大回りをして、結局は道に迷ったあたりの戻ってきて三越などある商店街を歩く、この商店街はいいくつか繋がった長い通りであった。
商店街の総称は高松中央商店街で、8つほどの地区が繋がっているようだ。商店街のほぼ全てを覆うアーケードは総延長が2.7kmあり、総延長では日本一。
但し、分岐を含まない連続的に連なったアーケードでの日本一は大阪市の天神橋筋商店街で総延長2.6kmという。
小売店や飲食店が約1000店舗(うち一階部分は約700店舗)が軒を連ね、一日の通行量は平日が約13万人、休日が約14万人となっており、平日・休日共に四国トップクラスの通行量。平日と休日の通行量にあまり差が無いのも特徴のようだ。
主に丸亀町周辺には全国チェーンの店や高級品を扱う店鋪が多く、南新町、常磐街などに南進する程に庶民的な店が増えて行く傾向にある。
近年では郊外の大型ショッピングセンターやロードサイド店舗に消費者が流れ、有力テナントが撤退するなど、状況は劣勢になって来ている。このため、現在は丸亀町、高松三越周辺では大規模な再開発事業が始まっているようで工事をしている個所もあった。
中心商業地区の真ん中に位置する「高松丸亀町商店街」は、全長470mの商店街。交差する道路を大きいドームにして各階が繋がっている、中々ユニークな形であるが、公道の上のために規制される法律はいくつもあってクリアするのに3年かかったという。
丸亀町は開町以来、400年余りの歴史を誇る町で、丸亀町という町名の由来は、天正16年(1588)に生駒正親が高松城築城の際、丸亀(現在の香川県丸亀市)の商人をこの地に移したことによるという。
さらに歩くが、そろそろホテル方向に向かうために、田町商店街なかほどでそれて栗林公園方面へいくのだ。ホテルは近くと思ったが随分と歩くことになった。

高松丸亀町商店街

上:高松丸亀町商店街 下左:田町商店街 下右:琴電