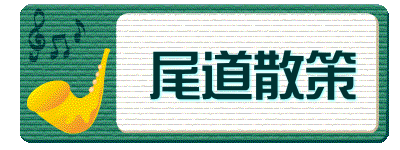(下)
帰りはバスでもいいのだが、ここから商店街を抜けて、大きい土産屋さんでおばちゃん連中の喜びそうな場所にも寄る。歩くのもしんどそうながら、買い物になると元気になるのだな。
大きい袋を持って出てくる人もいて、一辺に活動的になったような。再び暑い中を駅まで30分ほど歩く。予定よりも1時間早く到着して、ガイドさんとお別れの挨拶をする。電車まで1時間半以上あり、ここで自由行動だが、近くの喫茶店で休憩をして予定の電車で福山にでて、新幹線で大阪に戻った。
物足りない面もあったが、企画された人は早くから手配されて大変であったし尾道の眺望は良かった。やはり真夏でなくて春か秋にくればよかったようだ。ガイドさんも、今度はぜひ紅葉の頃や桜のころにきてくださいと言っていた。
機会があればゆっくりと、1泊するつもりで周辺を散策するのもいい場所だと思ったのだ。
7. おのみち映画資料館
この後は、文学の館とある「志賀直哉」「中村憲吉」「林扶美子」の旧居や、聖徳太子の創建を伝わる浄土寺などが予定では入っていたが、すべてカットで映画資料館だけみることになる。暑いので涼しいところに行くと言うことだ。
それでも30分ほど坂を下って街中を歩いてになる。おのみち映画資料館は、ゆかりの映画資料等を展示する博物館で、1998年(平成10年)の尾道市市制100周年、と1999年(平成11年)の西瀬戸自動車道(しまなみ海道)開通を機に推進された、「まちごと芸術・文化館構想」事業の一つという。
この付近は明治時代に尾道の海辺に軒を連ねた倉庫群の一つで、これを改装し、2000年(平成12年)に開館した。 入り口に映写機が置いてあるの面白い。
館内では尾道が舞台になった映画のロケ写真、約2万1千枚にものぼる上映当時の映画ポスターや100年前にフランスで初めて上映された劇場用映画の風景模型、昭和初期から最新のものまでの撮影機・映写機や8ミリフィルムなどが展示されている。
ここで、しばし涼んで休憩だ。入館者も少なくてゆっくりはできる。
* 写真 映画資料館入口に、古い映写機


6. 千光寺
千光寺には裏から入った形になったが、さすがに大勢の人がきている。狭い場所なので休憩もままならない。千光寺(せんこうじ)は今は千光寺公園内にある真言宗系の単立寺院。山号は大宝山(たいほうざん)。本尊は千手観音。中国三十三観音第十番札所、山陽花の寺二十四か寺第二十番札所。
境内からは尾道の市街地と瀬戸内海の尾道水道、向島等が一望でき、ここから取られた写真が観光案内などに使用されている。何度かきているが眺望はいいし空いていればゆくりできるのだが。
千光寺本堂は赤堂とも呼ばれる赤い建物だ。本尊千手観世音菩薩は、33年に一度開帳の秘仏。火伏せの観音とも称されている。試験合格、縁結び、子授け、交通安全、家内安全、夫婦円満、病気平癒、延命長寿等諸願成就の観音様としてお詣りが多いという。
鐘楼 大師堂前の小門をくぐると目前に朱塗り唐づくりの鐘楼が断崖絶壁に建っている。この鐘「驚音楼の鐘」は「時の鐘」として、元禄初年より時刻を近郷近海に報じ、尾道の名物の一つにもなっている。この鐘の特徴は鐘の上部に百八個のイボ(乳)がなく、梵字百字の真言と五智如来の種子が浮彫りになっている曼荼羅の鐘という。
他にも、毘沙門堂、鐘楼に、鏡岩、岩割松、鼓岩、千畳敷・八畳岩 などあるが、由来の説明は簡単ながら覚えられるものではない。ここだけが目的でないので先を急ぐというよりも、疲れ来て休みたいと思う人が多いのだ。
* 写真 3段目左:本堂、右:鐘楼、4段目:本堂裏手の三重岩

5. 文学のこみち
展望台下には食堂や喫茶店があるが休憩することなく下へ降りる道を歩く、この千光寺へ下る道を「文学のこみち」として整備されている。全長約1kmの遊歩道で、道沿いの自然の巨石に尾道ゆかりの作家・詩人による作品を刻んだ25基の石碑(文学碑)が立つ。横にはそれぞれ説明看板が付いている。
古くから観光地として有名で、多くの文人が訪れ、なかにはそれを記念して文学碑が作られた。1965年(昭和40年)・1969年(昭和44年)の2期にわたって尾道青年会議所が整備し、市に寄付したという。すべて見てはいないし、文字も読み取れない場所もあった。案内の方は先にどんどん行くので読んでいる時間はとれずだ。
そんな訳で写真もほとんど残らずになった。
* 写真 1段目左:文学のこみち碑、右:十返舎一九、2段目左:江見水陰、右:徳富蘇峰
3段目左:物外(もちうがい)右:判明しない