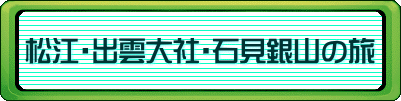帰りは坂道を下る方であり、ガイドさんに付いていると時間もかかるので、もうひとつの町並み散策に行くことにしてグループから離れて先に行くことにした。既に、最初から別行動の人たちもいたのだ。添乗員さんからは自由にしていいとなっていたのだ。
間歩までは2人で乗れるベロタクシー(三輪自転車)があって歩くよりは早いが料金はタクシー並だそうだ。天候によって中止の場合もある。また、レンタサイクルもあって貸し出しが行われているので、これを使う方法もあるようで、こちらは結構使っている人がいた。しかし、我々のツアーは誰も使わない、ガイドさんと一緒の行動になっていたのだ。
途中で清水寺を少し見てスタートした公園まできて大森町並みの方にいくが、手前の反対側に五百羅漢の前で写真のみ撮る。中に入る時間もなく急ぎ足なのだ。そして、戻って町並みを歩いて観世音寺まで行って戻ってしまった。まだ先があるが時間的にも危ないので、少し余裕をみて町並みは途中までで見たことになるとし諦めたのだ。
観世音寺は真言宗の寺院。幕末には儒学者佐和華谷が住持。岩山の上にあり、江戸時代には大森代官所が銀山隆盛を祈願するための祈願寺。本堂のほか山門と鐘楼が残されている。町並みの大半が焼失した「寛政の大火」寛政12年(1800)により観世音寺も全ての建物が焼失。創建年は不詳だが、現在の本堂や山門は万延元年(1860)に再建されたもの。という。少し高い場所にあるので、ここからの町並みの風景が一番よく見える。
銀山付地役人だった三宅家や、酒造業など営み有力な商家だった金森家など町並みを急ぎ足で少しだけ見てバスに戻る。後はひたすら岡山まで走り。岡山から新幹線で帰途についた。雨の影響や渋滞などで時間的には忙しい旅になったが、バスツアーではこういうものだ。
下
龍源寺間歩までは結構あって、次第に坂道の山道になっていく。
雨は幸いにもあがってくれて傘は不要になった。まだ降りそうな空模様ながらこの後は傘は使わずに済んで助かった。山道の方までくると人の通りも少なくなってくる。折角、石見銀山にきたのだから間歩を見ないとと思うが、実際には普通の舗装された薄暗いトンネルを歩くだけだ。ところどころに入り組んだ間歩が見られるのだが。
間歩は多数あって、今も当時の姿のまま入り口の穴が見られる。思ったよりも小さいが、これは個人で掘ったものという、個人で銀を掘り出して買い取ってもらうのだ。大規模なところは組織的に事業として実施していたという。上るにつれてこの穴が番号が振られて各所に見られる。いずれも廃坑で使えないものだ。
高橋家という当時の町年寄の家を過ぎて、いよいよ龍源寺間歩が近付くとやや急坂を上がる。先には入場券売り場があって、ここから有料域の間歩内に入る、暗いがところどころに電灯があって足元は何とか大丈夫。交差して狭い間歩が時々あるが、いずれも立ち入り禁止で入れない。狭いので一方通行になっていて真っ直ぐ行って突き当りを左に折れて、急な坂を上っていくとやがて出口だ。10分程度のものか。
出口にも間歩の跡があり、石見銀山の鉱床の説明があるが、看板の画像を最後に付けたので、それで見てもらうことにする。正直言って期待したほどではなかったが元に戻ることになる。他にもうひとつ公開されているが、予約制で料金も結構する見学コースがあるらしい。大久保間歩という石見銀山でも最大級の坑道。坑道内部では、江戸〜明治時代にかけての、人力から機械・火薬を用いた採掘痕の変化を見比べることができるという。残念だがこのツアーでは無理だ。
上の図で、右下の石見銀山公園から、左上の龍源寺間歩まで往復歩く
実際に歩きだして普通の山村であり、どこが世界遺産かと思うのだ。道筋は観光用に整備されているが銀山以外の目ぼしい見ものはないようだ。しかし、森林が茂り自然が残したままの山の地下には600を超える間歩があるらしい。閉山後は山地開発などなくてそのままの環境が残されたことがこの銀山を遺産として認められたのだ。
でも、ガイドさんから説明のあった、いくかの箇所を少しあげると、番所跡、徳川家康に見いだされ初代石見銀山奉行に任じられた大久保石見守墓所、17世紀初頭(江戸時代初め)の銀精錬遺跡の下河原吹屋跡は、鉛を利用した「灰吹」法と呼ばれる精錬法で銀を取り出していた。豊栄神社はかってこの地を支配していた毛利元就を祀ったところだが、草生して荒れ果てていた。


。
出雲大社から渋滞を抜けだして、ほぼ1時間程度でこの後は大きい渋滞もなく到着する。ここもバスの駐車場は降りた場所に留め置きはできずに、他へ移動する。結構広い駐車場ながら訪問が多いので置けないのだ。
このころは雨が降っていて、空も暗くて歩くにはあまりよくない。合羽を着こんで準備はしてきたが。ここもガイドさんが付いてくれる。ここからは2組に別れるのだ。公開している間歩(坑道)の見学組と町並み散策組になる。間歩まで約2.3KMの一部山道もあるところを歩くので、歩きが苦手な人のために散策組を設定したようだ。、
従ってガイドさんも二人で、ちょうどご夫婦であった。奥さんの方が話は上手いような感じしたが、奥さんは町並み組で、ご主人は間歩組になるが、ご主人も説明は熱心で丁寧であった。この地の住民で銀山の保護と世界遺産登録への苦労話など多彩な話題の持ち主だった。。
4.石見銀山
石見銀山は、戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期を迎えた日本最大の銀山(現在は閉山)。最盛期に日本は世界の銀の約3分の1を産出したとも推定され、石見銀山はほとんどの部分を占めていたという。また大森銀山(おおもりぎんざん)とも呼ばれ、江戸時代初期は佐摩銀山(さまぎんざん)とも呼ばれた。銀産出が少なくなった明治期以降は銅などの鉱物が主に採鉱された。しかし、価格の暴落や坑内の環境の悪化などにより大正12年(1923)に休山し、戦時中に再開するも水害で水没し完全閉山した。
石見銀山の歴史を調べると多数の文献があり、とても短時間には解釈できない。歴史は割愛して世界遺産のことを少しアップして先へ進む。平成19年(2007)に日本の世界遺産登録としては14件目、文化遺産としては11件目、産業遺産としてはアジア初の登録となるが、「山を崩したり森林を伐採したりせず、狭い坑道を掘り進んで採掘するという、環境に配慮した生産方式」という自然環境保護を訴求した運動が登録の決め手になったという。










 。
。