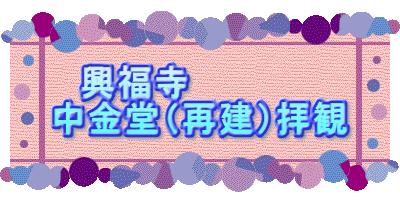談山神社の紅葉観賞の後は明日香まで歩き、バスで橿原神宮前駅に出て近鉄橿原線に乗車したが、途中で最近興福寺の中金堂が再建されたこと思い出し、回り道をして寄ってみることにした。
興福寺は南都六宗の一つ、法相宗の大本山の仏教寺院である。藤原氏の祖・藤原鎌足とその子息・藤原不比等ゆかりの寺院で、藤原氏の氏寺であり、古代から中世にかけて強大な勢力を誇った。
南円堂は西国三十三所第9番札所である。「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録されている。藤原鎌足夫人の鏡大王が夫の病気平癒を願い、鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として、天智天皇8年(669)山背国山階(現・京都府京都市山科区)に創建した山階寺(やましなでら)が起源。
壬申の乱のあった天武天皇元年(672)、山階寺は藤原京に移り、地名の高市郡厩坂をとって厩坂寺(うまやさかでら)と称した。和銅3年(710)の平城京への遷都に際し、鎌足の子不比等は厩坂寺を平城京左京の現在地に移転し「興福寺」と名付けた。
この710年が実質的な興福寺の創建年と言える。その後は度々火災に見舞われ、その都度再建を繰り返してきた。江戸時代の享保2年(1717)の火災の時は、時代背景の変化もあって大規模な復興はなされず、この時焼けた西金堂、講堂、南大門などは再建されなかった。
慶応4年(1868)に出された神仏分離令は、春日社と一体の信仰(神仏習合)が行われていた興福寺は子院は全て廃止、寺領は明治4年(1871)の上知令で没収された。
明治14年1881)、ようやく興福寺の再興が許可され、明治30年(1897)、文化財保護法の前身である「古社寺保存法」が公布されると、興福寺の諸堂塔も修理が行われ、徐々に寺観が整備されて現代に至っている。
興福寺中金堂は、藤原鎌足発願の釈迦三尊像を安置するための、寺の中心的な堂として和銅3年(710)の平城京遷都直後に造営が始められたと推定。後に東金堂・西金堂が建てられてからは中金堂と呼ばれている。
江戸時代の享保2年(1717)の火災焼失後は1世紀以上再建されず、文政2年(1819)、篤志家の寄付によって一回り以上小さい仮堂で再建されていた。
老朽化のため移築再利用も不可能で、一部の再利用できる木材を残して2000年に解体。創建当初の姿を再現した新・中金堂の建設と境内の整備が、創建1,300年となる平成22年(2010)に着工し、今年10月に落慶したのだ。
新中金堂は釈迦如来像を本尊とし、薬王・薬上菩薩像(いずれも重文)が脇侍として安置。須弥壇の四方は四天王像がかため、内陣には法相の14人の祖師を描いた「法相柱」を再現している。
創建当初の東西36.6m、南北23m、最高高21.2m、寄せ棟造、二重屋根、裳階付きで桁行(東西)9間、梁行(南北)6間の建物。近寄るには有料域になっているし、周囲の整備はまだ続いていて寄付を募る受付所も入口にある。
外国人観光客の訪問も多いのは、奈良公園への通り道にあたることもあるのだろう。
五重塔は、光明皇后の発願により、天平2年(730)に創建された。現存する五重塔は、室町時代中期・応永33年(1426)の再建。本瓦葺の三間五重塔婆である。文化財保護法に基づく国宝に指定されている。高さ50.1メートルで、現存する日本の木造塔としては、東寺五重塔に次いで高い。
興福寺 再建された中金堂

上:中金堂入口付近 下左:五重塔下部 下右:東金堂と五重塔

五重塔の前から猿沢池の方に降りて、池の周囲を歩き水面の移る五重塔を狙ったが曇っていてよくなかった。
猿沢池は、興福寺が行う「放生会」の放生池として、天平21年(749)に造られた人工池。放生会とは、万物の生命をいつくしみ、捕らえられた生き物を野に放つ宗教儀式である。
猿沢池の名前の由来は、インドのヴァイシャーリー国の猴池(びこういけ)から来たものと言われている。猴の字義としては、尾の短い種類のサルをさしているという。
名残はあるはこの日はここまでで帰途についた。
猿沢池